フェルミ推定はくだらない?企業が出題する理由や面白い問題を紹介![PR]
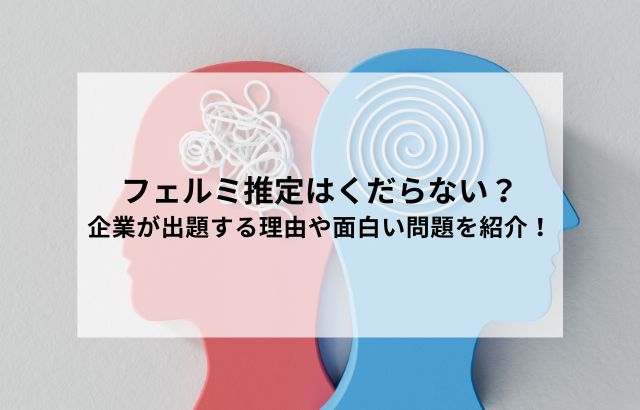
「フェルミ推定はくだらない?」
「企業がフェルミ推定を実施する理由は?」
という疑問をお持ちではありませんか?
本記事では、そんな疑問の解決に役立つ内容を
|
の順に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
フェルミ推定とは?

フェルミ推定とは、自分のもつ知識を使って、実際には調査できないような数量や規模を論理的に考え、短時間で答えを導き出す手法です。
例えば、「日本に電柱は何本あるか?」「日本の学生が1年間で消費するノートの枚数は?」など、実際に調査することが難しい質問が出題されます。
コンサルティングファームや投資銀行、総合商社などでは、候補者の論理的思考力を測るための選考でフェルミ推定が用いられることが多いです。
フェルミ推定を出題する目的
企業が選考でフェルミ推定を理由する理由は、「論理的思考や問題分解能力を試すため」と言えるでしょう。
論理的思考(ロジカルシンキング)とは、筋道を立てながら複雑な物事をシンプルに捉え直すスキルのことです。
問題分解能力は、問題の本質を見極めて解決策を考え出すスキルのことを指します。
コンサルティングファームや投資銀行、総合商社などの業界では、高度な論理的思考や問題分解能力が求められます。
そのため、候補者のポテンシャルを測るためにも、企業は選考でフェルミ推定を実施しています。
フェルミ推定はくだらない?

それでは、どうしてフェルミ推定はくだらないと言われているのでしょうか?
フェルミ推定はもともとGoogle社が選考に取り入れたことをきっかけに、多くの企業で活用されるようになりました。
しかし、現在Google社はフェルミ推定に否定的な立場を取っています。
以下で、フェルミ推定はくだらないと言われる理由を詳しく確認していきましょう。
フェルミ推定はくだらないと言われる理由
ここでは、フェルミ推定がくだらないと言われる理由を紹介します。
入社後の活躍度と相関がない
フェルミ推定はくだらないと言われる理由として、「フェルミ推定での評価」と「入社後の活躍度」に相関がないことが挙げられます。
先述した通り、Google社はフェルミ推定をいち早く選考に取り入れました。
しかし、フェルミ推定での評価が必ずしも入社後の活躍に結びつかないことから、Google社はフェルミ推定を実施することをストップしたのです。
フェルミ推定で優秀な回答ができる力と、実際に仕事で問われるスキルは必ずしも一致するとは限りません。
そのため、フェルミ推定で優秀な回答ができる能力と仕事で必要になる能力が一致している場合のみ、選考手段として有効と言えるでしょう。
選考のために対策ができる
フェルミ推定がくだらないと言われる理由の一つに、フェルミ推定は対策ができてしまうことが考えられます。
本来フェルミ推定は突拍子もないことが聞かれた際に、候補者が論理的思考力と問題解決能力を使って回答を導き出せるかという点を見るものです。
しかし、現在はフェルミ推定の対策本が販売されていたり、インターネットでも多くの情報が公開されていたりします。
そのため、その場での思考力を見極めづらくなっているのです。
優劣をつけづらい
優劣をつけづらい点も、フェルミ推定がくだらないと言われる理由のひとつです。
フェルミ推定で出題する問題は候補者によって異なるだけでなく、回答のパターンも幅広いです。
そのため、候補者が優秀かどうか判断するのは、候補者の視点に偏ったものになります。
フェルミ推定を選考に取り入れる場合は、採用担当者の中で評価基準や認識を統一させる必要があります。
企業がフェルミ推定を実施する理由

フェルミ推定には欠点があることを上記で紹介しました。
では、現在もフェルミ推定を実施している企業がいるのはどうしてでしょうか?以下で、フェルミ推定のメリットを確認していきましょう。
思考プロセスを評価できる
フェルミ推定は候補者の思考プロセスを評価するのに有効です。
コンサルタントとして活躍するためには、論理的思考を用いて数値を用いた仮説設定を行う必要があります。
もちろん、フェルミ推定で全てを測ることは難しいです。
しかし、候補者の思考プロセス(ポテンシャル)を把握することはできます。
複数のスキルを同時に確認できる
フェルミ推定では、候補者のさまざまなスキルを同時に確認することが可能です。
具体的には、フェルミ推定で測れるスキルとして、以下が挙げられます。
|
フェルミ推定はくだらないと言われる一方で、上記のようなメリットもあるため、フェルミ推定を実施している企業は少なくありません。
そのため、コンサルティングファームなどへの就職・転職を目指している方は、フェルミ推定の対策をしておくと良いでしょう。
\\おすすめランキング!//
フェルミ推定の面白い問題・例題

それでは、フェルミ推定ではどのような問題が出題されるのでしょうか?
以下で、フェルミ推定の面白い問題・例題を紹介します。
日本の電柱の本数は?
1つ目の例題は「日本には電柱が何本あるか?」という問題です。
まずは基本式を立案します。
電柱の場合は、「面積」×「面積あたりの本数」で算出すると良いでしょう。
しかし、人が住んでいない場所(主に山間部)や、人口が少ない田舎などを考慮する必要があります。
それぞれの場所ごとに電柱が何本程度必要かを設定し、計算を進めていきましょう。
東京メトロのコインロッカーの1日の売上は?
2つ目の例題は「東京メトロのコインロッカーの1日の売上は?」という問題です。
まずは、1日を平日にするのか、休日にするのかなど、前提の確認を行いましょう。
その次は基本式を立案していきます。
この問題の場合は、「東京メトロの駅数」×「一駅当たりのコインロッカー設置数」×「一コインロッカー当たりの口数」などの基本式が良いでしょう。
駅の大きさによってコインロッカーの利用率が異なるため、駅の大きさを大中小の3段階にセグメンテーションすることが大切です。
日本における缶コーヒーのマーケットサイズはどれくらい?
3つ目の例題は「日本における缶コーヒーのマーケットサイズはどれくらい?」という問題です。
缶コーヒーにカフェオレは含まれるのかなど、前提確認を行います。
基本式は「日本人口」×「コーヒー飲む人の割合」×「コーヒーを飲む頻度」×「缶コーヒー選択率」×「単価」などとすると良いでしょう。
年齢やライフスタイルに応じて、コーヒーを飲む人の割合を考えていきます。
他にも、コーヒーを飲む頻度を時間帯に分けて考えたり、ドリップコーヒーなどではなく缶コーヒーを選択するシーンを想定したりして、答えを算出していきましょう。
現在、地球上で何人が睡眠を取っているか?
4つ目の例題は「現在、地球上で何人が寝ているか」という問題です。
まずは夜の睡眠なのか、昼寝を含めるのかなど、前提確認を行いましょう。
寝ているかという問いなので、横になっている人を含めると良いかもしれません。
基本式は「世界の人口」×「寝ている人率」となります。
「今」という問いかけなので睡眠時間を「23時〜6時」に設定すると良いでしょう。
どこの地域が上記の時間に該当するか、人があまりいない地域はどこかなどを踏まえた上で、寝ている人率を考えていきます。
まとめ

今回の記事では、フェルミ推定の基礎知識をはじめ、くだらないと言われる理由や企業が実施する理由、フェルミ推定の面白い問題などを紹介しました。
フェルミ推定で確認できるスキルには限界があることや、フェルミ推定での評価と入社後の活躍に相関がないことなどから、フェルミ推定はくだらないと言われることがあります。
しかし、フェルミ推定にはメリットもあるので、選考に取り入れている企業は依然として存在します。
そのため、コンサルティング業界などを目指している場合は、フェルミ推定の対策を行っておくと良いかもしれません。
ITコンサル案件比較では、フリーコンサルタントに向けて、選考でのお役立ち情報や、案件獲得の方法などのコラムを多数公開しています。
おすすめのエージェントも紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
\\おすすめランキング!//








