常駐型コンサルタントはつまらない?メリット・デメリットを解説![PR]

「常駐型コンサルタントの仕事はつまらない?」
「常駐型コンサルタントとして活躍するには?」
という疑問をお持ちではありませんか?
本記事では、そんな疑問の解決に役立つ内容を
|
の順に解説します。
常駐型コンサルタントの働き方に興味がある方に役立つ記事です。
ぜひ最後までご覧ください。
常駐型コンサルタントはつまらない?

常駐型コンサルタントは、つまらないと言われることがあります。
常駐型コンサルタントの仕事について理解した上で、その理由を確認していきましょう。
常駐型コンサルタントとは
クライアントとの関わり方に関して、コンサルタントは大きく「非常駐型コンサルタント」と「常駐型コンサルタント」に分けられます。
常駐型コンサルタントとは、クライアントの社内に常駐してプロジェクトに参画するコンサルタントのことです。
常駐型コンサルタントは、①コンサルティングファームに所属しているコンサルタントが派遣されるケースと、②フリーランスのコンサルタントが配置されるケースがあります。
常駐型コンサルタントが必要なプロジェクト
非常駐型コンサルタントではなく、常駐型コンサルタントが必要になるプロジェクトとしては、以下の2つが挙げられるでしょう。
|
協業プロジェクトとは、コンサルティングファームとクライアントが協業で立ち上げるプロジェクトです。
新規事業立ち上げや戦略立案などを一緒に進めていくため、チームの一員として常駐することがあります。
オペレーション支援はRPAやSalesForce、SAPなどのソフトウェア導入支援等を手掛けるプロジェクトです。
現場の声を反映させるために常駐が必要なケースがあります。
常駐型コンサルタントがつまらないと言われる理由
常駐型コンサルタントがつまらないと言われる理由として、「高級文房具」や「高級派遣」と呼ばれるような仕事に対応するイメージが強いことが挙げられます。
「高級文房具」や「高級派遣」は、社内でも対応できるような業務であるにも関わらず、コストをかけてクライアントに依頼する状況を揶揄する言葉です。
業務効率化のためのアウトソーシングに近い形で依頼するクライアントが存在し、常駐型コンサルタントが雑務に対応するケースも少なくありません。
常駐型コンサルタントとして働くメリット

それでは、常駐型コンサルタントとして働くメリットはあるのでしょうか?
現場から直接ヒアリングできる
常駐型コンサルタントの強みとして、現場から直接ヒアリングできる点が挙げられます。
常駐型コンサルタントは社内の従業員とつないでもらいやすく、ヒアリング実施までの手間や時間を省くことが可能です。
一方、非常駐型コンサルタントはアポイントを取るところから、ヒアリングの機会を設定するところまでの調整が大変になります。
現場の声を取り入れながらプロジェクトを進めることで、より満足度の高い提案ができるでしょう。
さまざまな経験を積める
常駐型コンサルタントとして働くことによって、さまざまな経験を積むことが可能です。
非常駐型コンサルタントの場合、プロジェクト規模が大きい傾向にあり、1人のコンサルタントが対応する領域も制限されます。
しかし、常駐型コンサルタントの場合、比較的小規模なクライアントに常駐することが多く、コンサルタントの対応領域が広がります。
コンサルタントとしてのスキルを高めたい方は、常駐型コンサルタントの働き方も検討してみましょう。
一貫した支援ができる
一貫した支援ができる点も常駐型コンサルタントのメリットと言えます。
例えば、新規事業立ち上げをクライアントと協業で実施していく場合、プロジェクトの立ち上げから経験することができます。
プロジェクトの上流工程から下流工程まで幅広い経験を積むことで、プロジェクトマネージャーへのステップアップも実現しやすくなるでしょう。
シニアアソシエイトをはじめとしたコンサルタントの役職については、以下の記事で解説しています。
\\おすすめランキング!//
常駐型コンサルタントとして働くデメリット
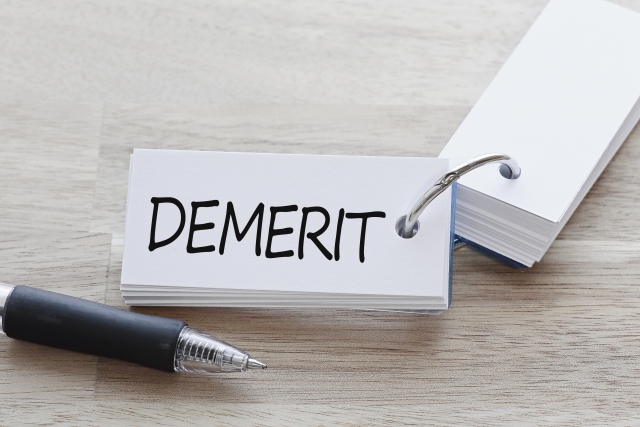
それでは、常駐型コンサルタントとして働くデメリットはあるのでしょうか?
働き方の自由度が低い
常駐型コンサルタントとして働くデメリットは、働き方の自由度が低い点です。
クライアントのオフィスに出勤して働くことになるため、場所や時間の自由度が低くなります。
また、クライアントの社員に気を遣いながら仕事に取り組まなくてはいけません。
より自由度の高い働き方を実現したい方は、フリーランスの働き方も検討してみましょう。
フリーランスは「週10時間からの稼働」「リモートワーク」など、希望にあった案件を選ぶことができます。
加えて、フリーランスの方が高収入を目指しやすいです。
専門的なスキルが身につきづらい
専門的なスキルが身につきづらい点も、常駐型コンサルタントのデメリットと言えます。
プロジェクトにもよりますが、常駐型コンサルタントは「何でも屋」になりやすいです。
資料作成などの雑務に対応することも多く、専門的なスキルを伸ばせません。
専門的なスキルを身につけたい場合は、常駐型コンサルタント以外の働き方を検討すると良いでしょう。
高級文具プロジェクトで終わる可能性がある
先述した通り、高級文具プロジェクトとはクライアントが社内で対応できるような業務を効率化させるために、コストをかけてコンサルタントに依頼することです。
常駐型コンサルタントは高級文具プロジェクトに対応するケースも多く、イメージとは異なる仕事を任される可能性もあります。
常駐型コンサルタントとして活躍する方法

それでは、常駐型コンサルタントとして活躍するにはどうすればいいのでしょうか?
コンサルタントとしてのスキルを高める
どのようなプロジェクトにアサインされたとしても、コンサルタントに求められる根本的なスキルは変わりません。
具体的には、以下のスキルが挙げられます。
|
高級文具プロジェクトであっても取り組み方によっては、コンサルタントとしてのスキルを向上させることができます。
常駐先ごとの知識をインプットする
常駐型のクライアントごとに必要なスキルや知識が変わってきます。
例えば、業界に関するニュースや競合の状況、クライアントの事業内容など、プロジェクトに応じて様々な知識を身につけることが重要です。
こういった前提知識がないと、クライアントとの話し合いについていけずに、コンサルタントとしての信頼性が失われてしまうでしょう。
自分にあった働き方を考える
自分にあった働き方を考えることも重要です。
常駐型コンサルタントの働き方が合う人もいますし、より自由度の高い働き方が向いている人もいます。
新しい環境が苦にならない、チームでの作業が得意といった人は、常駐型コンサルタントに適しているかもしれません。
そもそもコンサルタントという仕事が自分にあっているかという点も含めて、自分のキャリアについても検討してみましょう。
コンサルタントはやめとけと言われる理由については、下記を参考にしてください。
まとめ

今回の記事では、常駐型コンサルタントがつまらないと言われる理由について解説しました。
常駐型コンサルタントは高級文房具のような働き方をするケースも多く、プロジェクトへの取り組み方によって自分のスキルを伸ばせません。
主体的になって働きたい方や、自分の興味のあるプロジェクトに携わりたい方は、フリーランスの働き方を検討してみましょう。
ITコンサル案件比較はフリーコンサルタントに向けて、案件獲得や職種についてのお役立ち情報を紹介しています。
\\おすすめランキング!//








